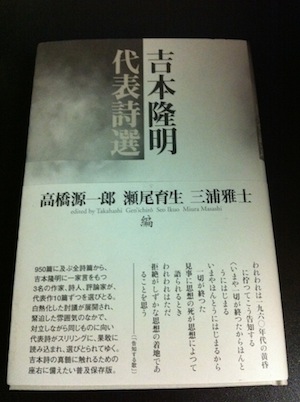心の脂肪。
星海社の柿内さんがおもしろいことを言っている。
楽しいかどうかはわからないけど、
かつてプロレスファンだった人間として、ちょっと書いてみたい。
プロレスがおもしろくなくなったと言われて久しい。
実際ぼくもそう思うし、いまでは観る気も起きない。
なぜ、おもしろくなくなったのか?
人によっていろんな解釈があるだろうが、
なにより決定的だったのは弱小団体の乱立である。
プロレスがゴールデンタイムで放送され、
国民的人気を誇っていた当時、日本のプロレス界は
・新日本プロレス(アントニオ猪木の団体)
・全日本プロレス(ジャイアント馬場の団体)
の2大メジャー団体が牛耳っていた。
議論をわかりやすくするため、ここでは
アントニオ猪木率いる新日本プロレスに話を絞ろう。
たとえばローリング・ストーンズのコンサートでは、
いまだに60年のヒット曲を歌わないとお客さんが満足しない。
エリック・クラプトンは毎晩のように『いとしのレイラ』を演奏し、
桑田佳祐は『いとしのエリー』を歌う。
これは興行のさだめだろう。
そして興行会社たるプロレス団体では、
毎晩のようにアントニオ猪木が勝たなければいけない。
シリーズ最終戦に向けての伏線として
まさかの敗北!を喫することはあっても、
基本的には「猪木が勝つ」のが興行のルールなのだ。
実際にアントニオ猪木が人気・実力ともに他を凌駕していた
70年代から80年代前半あたりまでは、それでよかった。
猪木が勝つ、という興行に説得力があった。
しかし、80年代後半あたりから
猪木の肉体的・精神的な衰えが目立つようになり、
それと入れ替わるように中堅レスラーの人気・実力が上昇し、
興行としての説得力に陰りが見えるようになる。
おそらく中堅レスラーの中には
自分がトップになればもっとおもしろい試合ができる、
もっと客を集めることができる、
新しいプロレスを体現することができる、
との自負もあっただろう。
実力的には猪木を上回りながら
いつまでも引き立て役を強いられる会社のシステムにも
不満がたまっていたのだろう。
80年代後半からの新日本プロレスは、
中堅レスラーの相次ぐ流出(独立)に悩まされるようになる。
では、独立したレスラーたちはどうなったか?
……やはり興行会社のジレンマに苦しむのだ。
自分が設立した小さな団体で興行を打っていく。
当然、スポンサー周りも必要になるし、
全国各地の興行主との飲み会・接待に忙殺されるようになる。
練習時間が奪われるのはもちろん、
睡眠時間を確保することさえままならない。
しかも新団体の設立当初は、自前の道場を持つことも難しい。
スパーリングの機会もなくなり、
ぶっつけ本番の粗い試合ばかりが続くようになる。
結局、独立していったレスラーたちの筋肉は衰え、
その身体はでっぷりとした脂肪に覆われていくことになるのだ。
しかも皮肉なことに、
彼らは興行会社の社長として、勝ち続けなければならない。
かつて自分が反旗を翻したアントニオ猪木がそうだったように。
さてこの話、
一般企業にも通じるところがないだろうか?
大きな会社に属し、エース級の働きをしながら認められない。
会社のシステム自体を変えるには至らない。
そこで独立・新会社設立を決意するも、
今度は社長業に忙殺され、
プレーヤーとしての筋力が衰え、脂肪がついていく。
会社員時代にできていた「スパーリング」の機会もなくなり、
すべての仕事が一発勝負になる。
目の前の仕事に追われ、長期的視野を持てなくなる。
よく言われるように、
プレーヤーとマネージャーの才覚はまったくの別物だ。
僕は優秀なプレーヤーが独立していくことは
時代の必然だと思っている。
でもその場合は、自分がプレーヤーでなくなった場合の
心の脂肪に気をつけなければならない。
あるいはいっそのこと、外部から経営者を雇うことだ。
経営なんて、職種のひとつに過ぎないのだから。