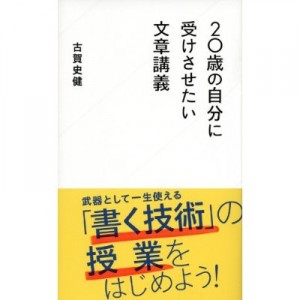前回から日が空いてしまいました。
取材時に気をつけること、その続きです。
緊張してるのはあなただけじゃない。
ここで信頼関係の構築に失敗してしまうと、
相手は無難に取材を終わらせようと、「いつもの話」を始めてしまう。
だから、事前にたくさんの資料を読み込んで、
「あなたのことをこんなに調べてきましたよ」
「わたしを信用しても大丈夫ですよ」
というサインを送る必要がある。
言葉で伝える必要はない。読んでいれば、自然と伝わる。
ライターにとって大切なのは、
いかにして「いつもの話」から脱するか? という問いかけなのだ。
前回はそんな話をしました。

それでは「いつもの話」に流れようとする取材相手に対して、
どんな質問をしていけばいいのでしょう?
どうすれば信頼関係を築くことができるのでしょう?
これはかなり難しい問題だと思います。
いまのところ、ぼくの暫定的な答えは次の一点です。
●質問の主語を意識的に使い分ける
取材のなかでライターは、取材相手にさまざまな質問をします。
そして質問とは、基本的に「わからないから」するものです。
または「もっと知りたいから」するものです。
では、ここで「わからない」と思っているのは誰なのでしょう?
いったい誰が「もっと知りたい」と思っているのでしょう?
取材のなかで相手に質問するとき、
この点をあいまいにしている人は多いのではないでしょうか。
ぼくは、
それが「読者の質問」なのか、
あるいは「わたしの質問」なのか、
質問の主体を明確に使い分けるよう、心掛けています。
なぜか?
基礎的な質問、かつ客観的な質問は「読者の質問」です。
具体的な質問、かつ主観的な質問は「わたしの質問」です。
いい原稿を書くためには、
「なにを今さら」と言われかねないような、
取材相手の基本情報も盛り込まなければなりません。
たとえあなたがその人の著書を50冊読み込んでいたとしても、
あえて基本情報(いつもの話)を聞く必要がある。
原稿の向こうに「なにも知らない読者」がいる可能性がある以上、
これは当たり前のことでしょう。
ということは、
取材が「いつもの話」だけで終わってはいけないけど、
なにも知らない読者のことを考えると「いつもの話」がゼロでもいけない。
おそらく取材の1~3割くらいは「いつもの話」になるし、
そうあるべきだと思います。
ただし、
これら「いつもの話」を引き出すにあたっては、
「まずは読者のために、○○のポイントについて聞かせてください」
「読者からすると、なぜ○○なのか疑問に思うかもしれませんね」
など、質問の主体が読者であることを明確にする。
こうすれば相手も
「なるほど、このライターさんはちゃんと調べた上で、
一般の読者にもわかるように基礎的なところから質問しているんだな」
と思ってくれるかもしれません。
そして語られた「いつもの話」に対して、
「それについて、ぼくが思ったのは…」
「まさにそこをお伺いしたくて、今日の取材を楽しみにしていたのですが」
といった具体的な「わたしの質問」を差し挟んでいく。
読者なんて関係ない、とにかく自分が知りたいのだ、という態度を明確にする。
こうすれば自分が事前に資料を読み込み、多くの考えをめぐらせてきたこと、
真剣に考えてきたことも伝わっていくはずです。
相手も信頼してくれるでしょうし、
さすがに「いつもの話」一辺倒ではなくなるでしょう。
もちろん、そのためには
事前にたくさんの資料を読んで、自分の頭で考え抜かなければなりません。
つまり、
原稿のアウトラインは「読者の質問」によって形成し、
原稿の妙味となる部分は「わたしの質問」によって引き出していく。
そして取材現場には、
・読者代表としての自分
・他の誰でもない「わたし」としての自分
・取材相手
の3人が同席している感覚です。
その流れで言うと、
取材とは、インタビュアー(聞き手)とインタビュイー(話し手)が
対峙するようなものではないと、ぼくは思っています。
むしろ、聞き手と話し手の両者がガッチリと肩を組み、
同じ方向を向いて、知恵と言葉を出し合って、
「どうすれば読者に伝わるか?」を考えていく共同作業の場こそ、
理想的な取材なのではないかと思います。
「読者の質問」と「わたしの質問」とを上手に使い分けることは、
その第一歩になるのではないでしょうか。